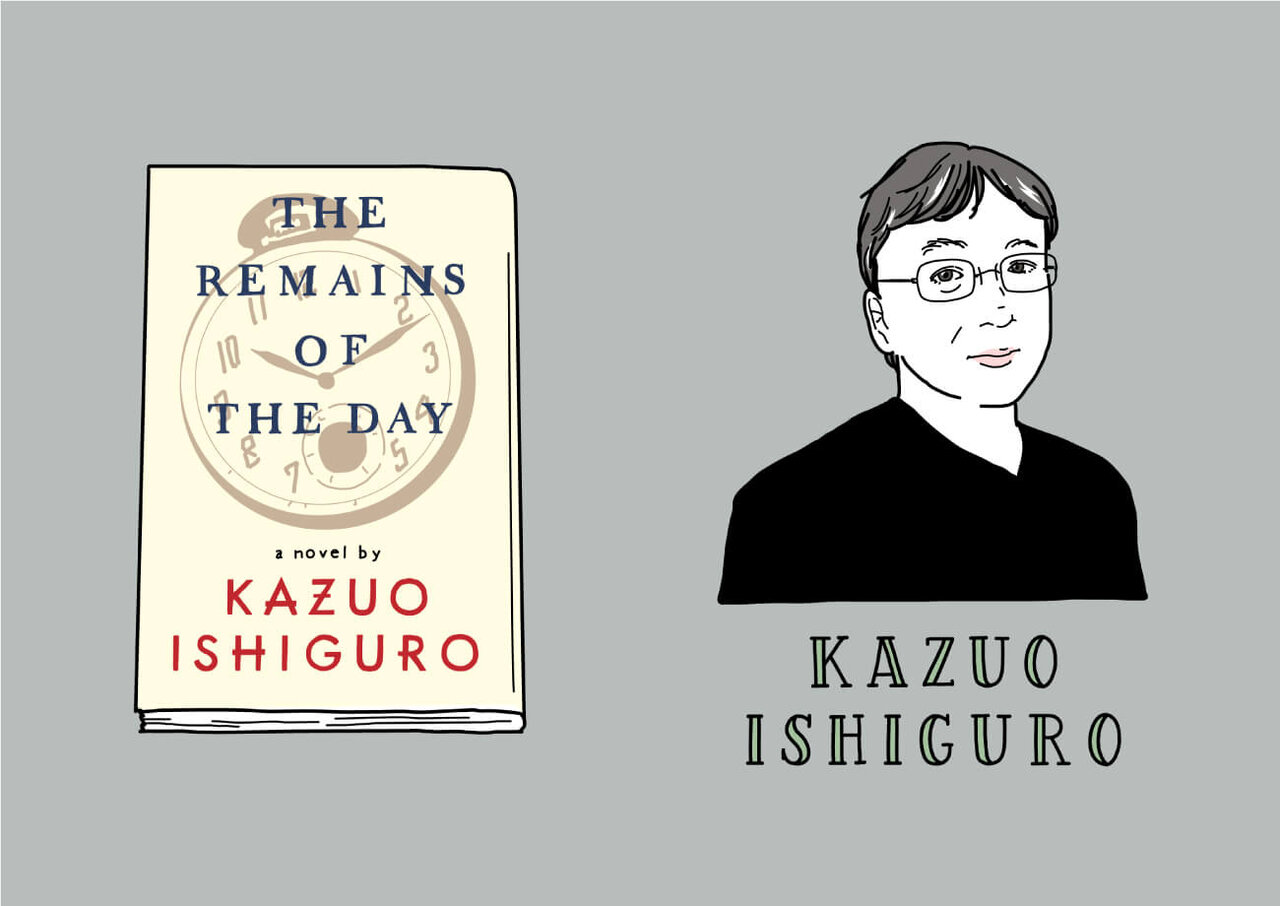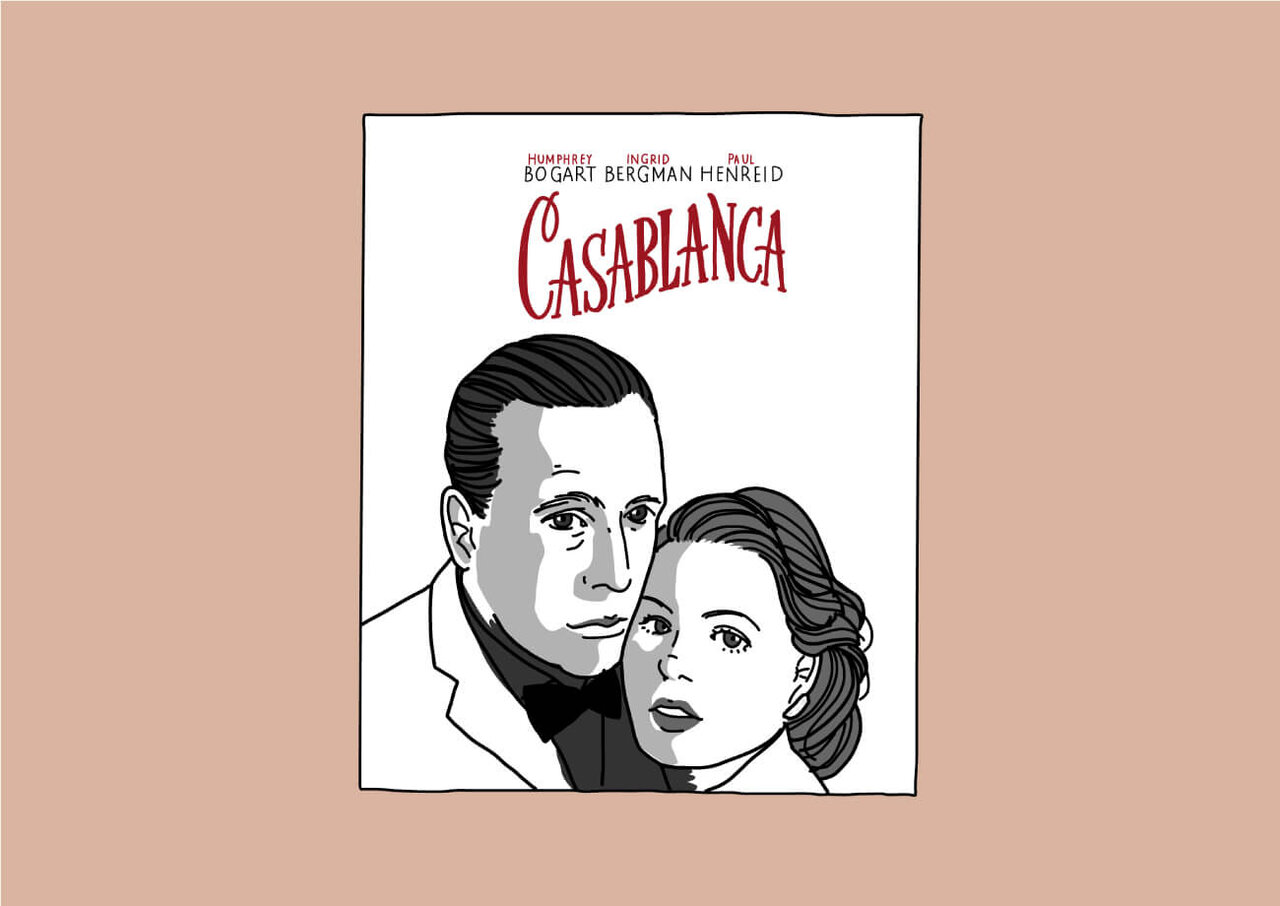前回担当した本コラムでは、『パラサイト 半地下の家族』を“プロダクション・デザイン”という観点から読み解くことで、映画の中で登場する数々の“モノ”がいかに多くのことを語っているかについて探っていった。今回は2020年5月1日に配信されて以来、ここ日本でも(会社や学校の多くはリモートもしくは閉鎖中だったので)ネット上で熱烈に支持されているNetflixオリジナル映画『ハーフ・オブ・イット:面白いのはこれから』を取り上げて、“モノ”は“モノ”でも作品の中で具体的に出てくる文学作品や映画に焦点を当ててみたい。
優れた映画は、過去の映画へのレファレンスはもちろんのこと、作り手がそれまで吸収してきたあらゆる芸術作品を通して培われた素養の上で成り立っている(逆に、総合芸術である映画の場合は、そうした背景の欠けた作品には優れた作品などないとさえ言える)。映画批評の役割の一つは、作品を観てその影響元を推察したり、作中にこっそりと隠されたサイン(例えば、主人公の部屋の本棚にチラッと映ってるとか)を見つけて考察することなのだが、『ハーフ・オブ・イット』ではそれがほのめかしのレベルではなく、まるでパッチワークのように作品全編に数々の文学作品や映画の直接的な引用が張り巡らされている。
監督、脚本、製作を手がけたアリス・ウーは、1970年カリフォルニア州サンノゼ生まれ。台湾からの移民である両親に育てられ、16歳でマサチューセッツ工科大学に入学、その後スタンフォード大学でコンピューターサイエンスの博士号を取得し、20代はマイクロソフトでソフトウェアを開発していたという、かなり異色のキャリアを歩んできた映画作家。アメリカの田舎(架空の町)の高校を舞台にした、普遍的であると同時にまったく新しい三角関係を描いたラブコメディ『ハーフ・オブ・イット』には、レズビアンであることをカミングアウトしている彼女の実人生が反映されている。
『ハーフ・オブ・イット』の素晴らしさは、作中で引用された文学作品や映画をまったく読んだことも見たこともない人でも楽しめるところにあるのだが、そこに込められた意味を知れば作品に何倍も感動すること間違いないだろう。まだ観ていない方はもちろんのこと、一度観た方も本稿を手がかりに再見(それが気軽にできるのが配信作品のいいところ)してみてほしい。(編集/メルカリマガジン編集部、イラスト/二階堂ちはる)
文学作品
プラトン『饗宴』
『ハーフ・オブ・イット』は冒頭からいきなりプラトンの引用から始まる。そう、あの古代ギリシアの哲学者プラトンだ。画面に映し出されるのは『饗宴』の中の次の一文、「愛とは完全性に対する欲望と追求である」。それに続くオープニングのアニメーションで、その意味するところがわかりやすく説明される。要は、人はみな、生まれた瞬間に切り離された「自分の半身」(ハーフ・オブ・イット)を探し求めている、その行為こそが愛だということ。ちなみにプラトンの師であるソクラテスは著作を一作も残してない(著作とされているものは、すべて弟子などが書き残したもの)ことで知られているが、プラトンの著作もその多くは対話篇と称される戯曲形式で残されていて、引用元の『饗宴』もその一つ。
オスカー・ワイルド『ドリアン・グレイの肖像』
文才に長けた地味な優等生エリーは、アメフト部に所属する同級生ポールから、学内人気ナンバーワン的存在の美女、アスターへのラブレターの代筆を頼まれる。そこからポール(書いてるのはエリー)とアスターの手紙のやりとりが始まるところで画面に映し出されるのは、19世紀末ヴィクトリア朝時代の英国文学を代表する詩人・戯曲家オスカー・ワイルドの長編小説『ドリアン・グレイの肖像』からの次の一文。「自分を欺いて始まり、他人を欺いて終わる。それが恋愛だ」。実はエリーもまた、アスターに淡い想いを寄せていた。オスカー・ワイルドは、当時の英国社会でタブーとされていた男色を咎められて1895年に投獄される。退廃的な生活を送る美青年の半生を描いた『ドリアン・グレイの肖像』は、ワイルド自身の実生活を反映した作品として、その時の裁判で証拠として提出された。
カズオ・イシグロ『日の名残り』
エリーとアスターが最初に言葉を交わしたのは、校内の廊下でエリーが落としたカズオ・イシグロ『日の名残り』をアスターが拾ってくれた時だった。2017年にノーベル文学賞を受賞した日系英国人作家カズオ・イシグロの代表作である本作は、長年執事として主人に仕えてきた主人公が、過去の果たせなかった自分の使命と恋について想いを巡らす回想形式の小説。アスターはエリーに本を渡した時、「私もこの小説好き。主人公の抑えきれない気持ちがわかる」と作品の核心を突く一言を発する。普段は学内のモテ系女子グループと他愛のない話に興じているアスターの意外な一面に触れたことで、エリーのアスターへの想いは高まっていく。また、エリーがカズオ・イシグロの本を読んでいた理由としては、幼少期に日本から英国に渡ったカズオ・イシグロと、幼少期に中国からアメリカに渡ったエリーの境遇の近さにも注目すべきだろう。
ジャン・ポール・サルトル『出口なし』
物語序盤の授業シーン、中盤のアスターとのデートを控えたポールにエリーが一夜漬けでカルチャー全般の教養を指南するシーン、そして終盤に画面に映し出される引用と、『ハーフ・オブ・イット』全編を通じて何度も言及されるのが、フランス20世紀実存主義文学を代表する作家、ジャン・ポール・サルトルの戯曲『出口なし』だ。作中で引用される「地獄とは他人である」という一文は、本作のテーマを最も端的に表している。女性2人と男性1人、死んで地獄へと送られた3人だったが、その地獄とは鍵のかかった密室だったーーそんな『出口なし』の設定は、強固なカトリック的価値観によって家族のあり方や恋愛のあり方が縛られた小さな町で生活している、エリー、アスター、ポールの置かれている状況と重なる。ちなみに、『出口なし』に登場する2人の女性のうちイネスは同性愛者、もう1人のエステルはアスターという名前の由来だろう。
『ハーフ・オブ・イット』の終盤にはもう2つ、「愛は厄介でおぞましくて利己的...それに大胆」という一文と、「パイナップル」と「フクロウ」と「毛虫」の絵文字が画面に映し出される。この世界に“真実”や“意味”とされるものがあることを信じて疑わない古代ギリシアの哲学者プラトンの言葉から、現代の高校生がスマホで交わす“無意味”な絵文字へと至る過程で、本作のタイトルの由来でもある「愛とは完全性に対する欲望と追求である」という言葉がどのように鮮やかにひっくり返されるのか、是非その目で確かめてほしい。
映画
『カサブランカ』(1942)
『ハーフ・オブ・イット』の作中で言及される文学作品の多くは、画面に文章が映し出されるという非常にわかりやすい手法で引用されている。では、映画はというと、妻が亡くなって以来、家に籠って塞ぎがちなエリーの父エドウィンが、現実から逃避するようにリビングで名作映画を観続けている、そのテレビの画面を通して観客(視聴者)に提示されていく。作中で最初にテレビ画面に映し出されるのは、ハンフリー・ボガートとイングリッド・バーグマンによるラブロマンスの名作『カサブランカ』の超有名なラストシーン。最後のセリフ「これは美しい友情の始まりだ」は、そのまま『ハーフ・オブ・イット』の物語の行方を示唆している。
『ベルリン・天使の詩』(1987)
ポールからアスターへのラブレターの代筆を引き受けたものの、アスターを想うエリーは当然のように気乗りしない。そんなエリーの視線の先に、父エドウィンがテレビで見ているヴィム・ヴェンダーズ『ベルリン 天使の詩』のセリフの英語字幕が映し出される。「渇望してる。愛の波に満たされるのを」。思わずエリーはそれを手紙で引用してしまうが、アスターはポールに宛てた返事の手紙でその引用元をズバリ言い当ててみせる。『日の名残り』について高校の廊下で交わした短い会話に続いて、エリーはアスターの文化的教養の豊かさに驚かされることになる。「どうしてズルをしたんだ?」とエリーを責めるポール。エリーやアスターのような人々にとって、芸術作品の引用のやり取りこそが最も高度な愛の交歓であるということに、きっと彼は永遠に気づくことはない。
『フィラデルフィア物語』『ヒズ・ガール・フライデー』(1940)
『ベルリン・天使の詩』のような80年代のヨーロッパのアート映画から、『野獣一匹』のような現代のインドの大衆映画(途中で寝落ちしてるが)まで、映画好きとしてはかなり雑食気味の父エドウィンだが、どうやら最も愛着があるのは30〜40年代のハリウッド黄金時代の作品のようだ。いずれもケーリー・グラント主演作となる『フィラデルフィア物語』(ジョージ・キューカー監督)と『ヒズ・ガール・フライデー』(ハワード・ホークス監督)は、当時のハリウッドが量産していたスクリューボール・コメディの代表的な傑作。同ジャンルの基本となるのは恋愛を巡る男女の三角関係と、終盤に向けて物語が急転換していくストーリーテリングだが、いかにもミレニアル世代以降のインディペンデント映画らしいシンプル&クリーンな佇まいを持つ『ハーフ・オブ・イット』も、実はまったく同じ構造を持っていたことが最後に判明する。
『街の灯』(1931)
『ハーフ・オブ・イット』で心温まるサブストーリーとなるのは、エリーの父エドウィンとポールのささやかな交流だ。そのきっかけとなるのが、エリーの家に上がり込んだポールが、エドウィンが観ているチャールズ・チャップリン『街の灯』に身を乗り出すシーン。ポールにとっておそらくは生まれて初めて観るサイレント映画。それなのに、何の先入観もなく作品に夢中になれる素直さがポールの最大の魅力であり、やがてエドウィンもそんな彼には心を開いていく。また、『街の灯』が描いている最初のボタンの掛け違いがもたらす悲恋も、そのまま『ハーフ・オブ・イット』全体のストーリーへと重なっていく。文系としての天才的なセンスだけでなく、かつてマイクロソフト社でソフトウェアを開発していたのも納得の、アリス・ウー監督によって周到に仕掛けられた引用作品の数々と本作との精密なリンクには、感嘆のため息をつくしかない。
戯曲『シラノ・ド・ベルジュラック』
以上、古今東西、様々な文学作品や映画の引用が散りばめられていて、それらが映画としての「語り」の力を高めている傑作『ハーフ・オブ・イット』だが、最も大きな影響元は作中では描かれていない。『ハーフ・オブ・イット』の「ラブレターの代筆から始まる三角関係」という基本ストーリーラインは、実は17世紀の剣豪作家シラノ・ド・ベルジュラックを主人公とした戯曲『シラノ・ド・ベルジュラック』そのもの。これまで世界中で数えきれないほど何度も再演されて、何度も映画化されて、ここ日本でも時代劇の原案や宝塚の演目にもなってきた古典中の古典だ。それがこんなにフレッシュな青春映画として生まれ変わってしまうところに、映画という表現形式の面白さが凝縮されていると言っていいだろう。“リメイク”、“リブート”、“オマージュ”、あるいは“パクり”だとか、そんな言葉では言い表せないもっと大切な歴史への敬意とその継続性が、『ハーフ・オブ・イット』のような本当に優れた映画にはあるのだ。
Netflix映画『ハーフ・オブ・イット: 面白いのはこれから』独占配信中
成績優秀で内気なエリーは、優しいけれど奥手なアメフト男子ポールに頼まれて、高校で一番人気の女の子に告白する手助けをすることに。ところが、エリーが自分自身も彼女に惹かれていると気づいたことから、思いもよらずに芽生えたポールとの友情はこじれていき...。