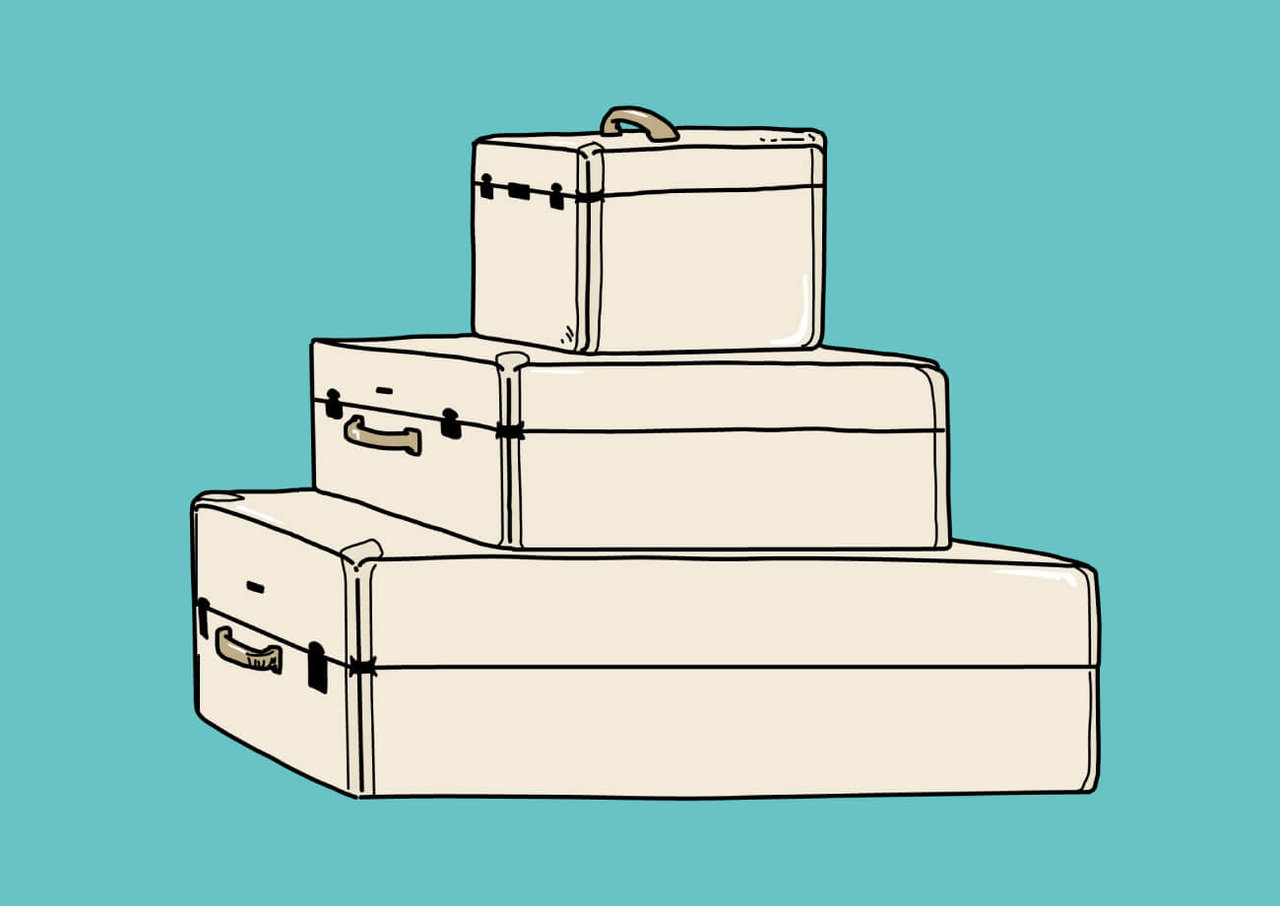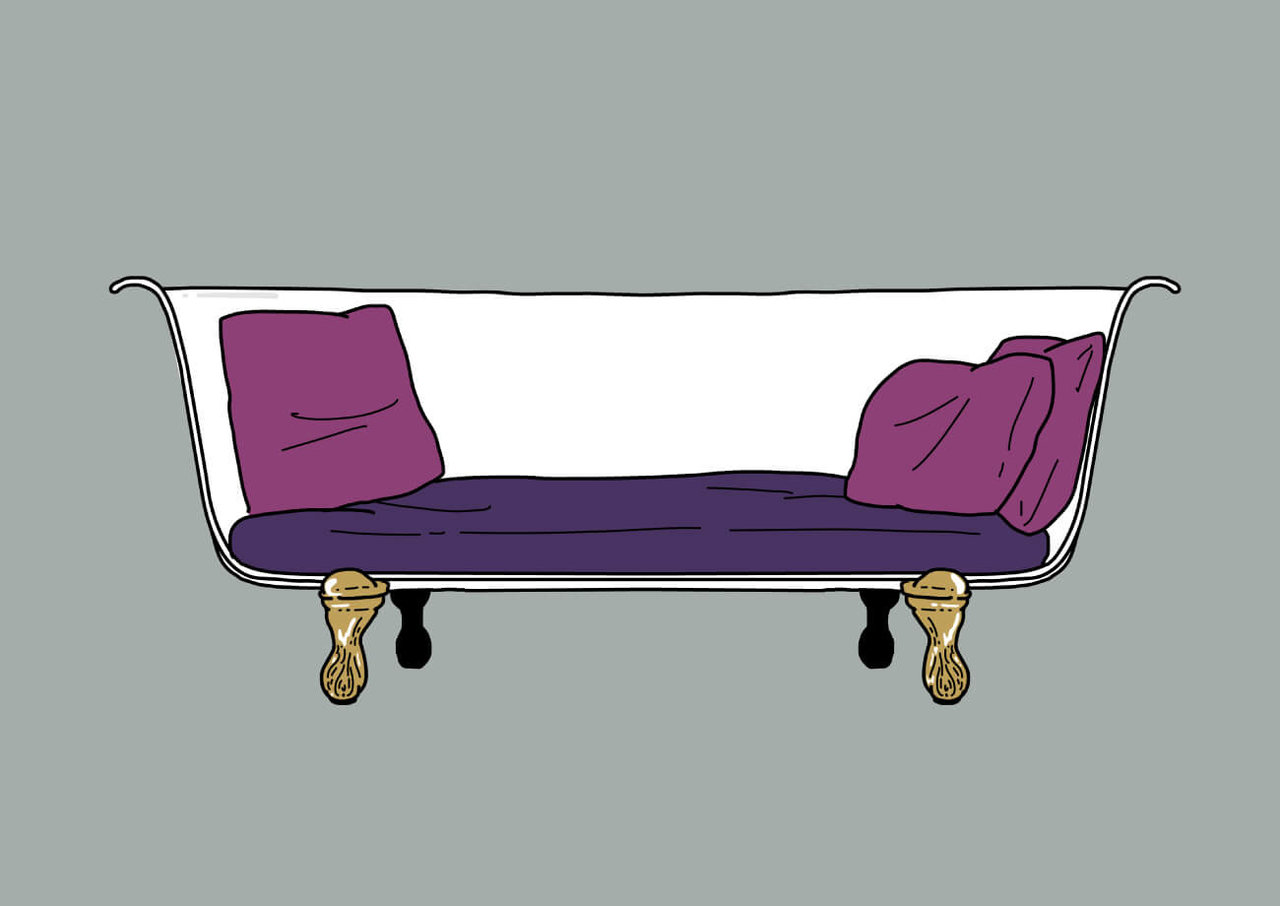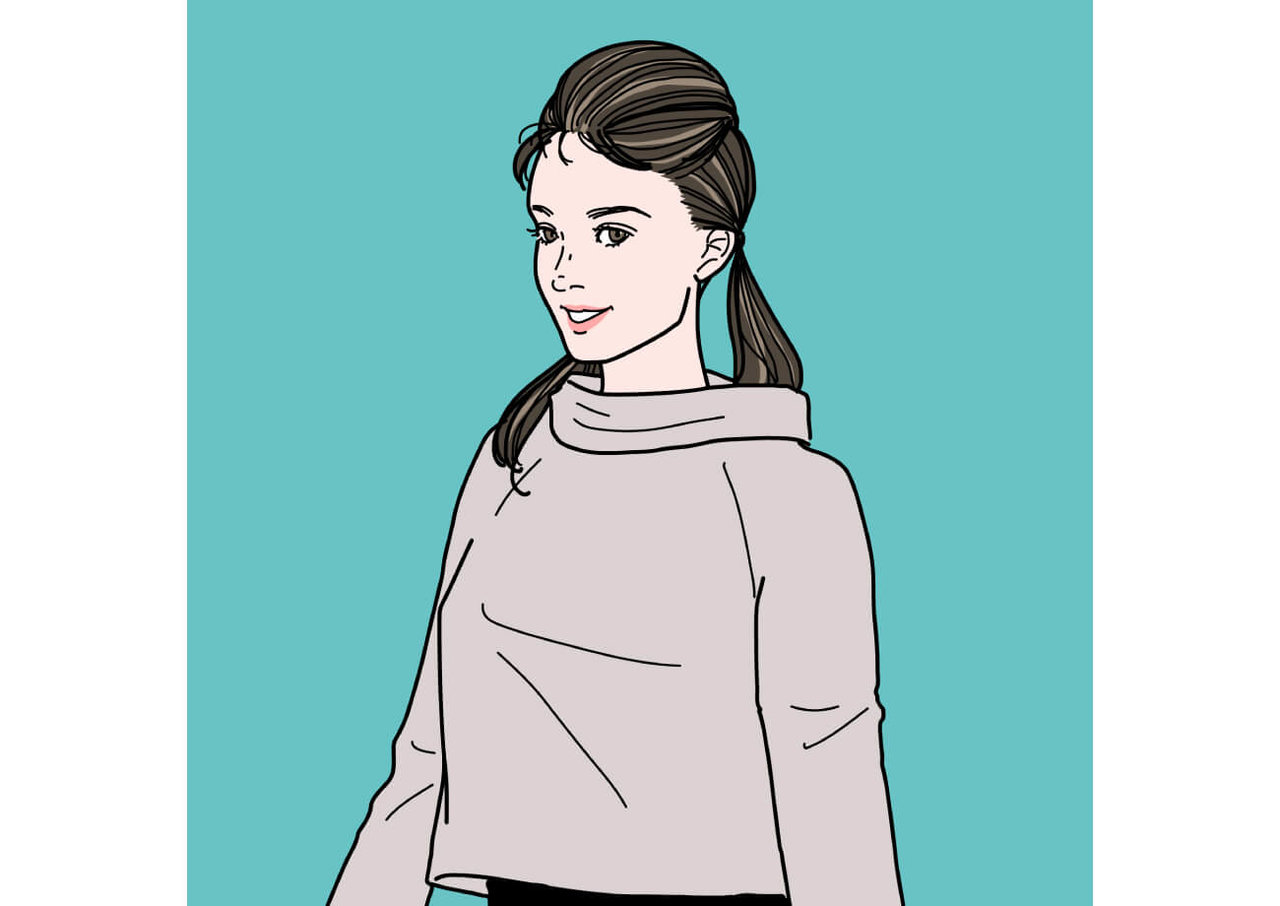あの作品の“モノ”を徹底リサーチ #02
映画やドラマや小説に登場するモノは、ときに人物と同じように語り、演じ、物語の世界を作り上げます。山崎まどかさんは、ニューヨークという街で女の子が奮闘する映画に注目。1961年に一世を風靡した『ティファニーで朝食を』から約60年、大都会で生きるヒロインのライフスタイルは、どんな変化を遂げてきたのでしょうか。経済状況や女性と社会の関係も移ろう中、夢を追いかける彼女たちの持ち物や服装は――? 現代が舞台のノア・バームバック監督『フランシス・ハ』、レナ・ダナム監督『タイニー・ファニチャー』とともに、作中の“モノ”からその背景を解読していきます。(編集/メルカリマガジン編集部、イラスト/二階堂ちはる)
ニューヨークの女の子たち、特に若い独身の女の子はどんな部屋に暮らしているのだろう? この街を舞台にした映画を見ると、いつもヒロインが住んでいるアパートメントのインテリアについ目がいってしまう。ゴージャスなマンションよりも、どこか現実感のある部屋に惹かれる。自由を求めてこの街に来ても、何もかもが手に入る訳ではない。マンハッタンの家賃は高いし、若い女性の収入は限られている。それでも、自分らしい居場所を作るための工夫一つで、この都会は彼女たちが生きる場所になる。マンハッタンを舞台にした映画で、私が気になったヒロインたちの部屋や小物のディテールをいくつか紹介したい。
ドロワー代わりのトランク
マンハッタンのシングル・ガール・アイコンとして外せないのが「ティファニーで朝食を」(1961)のホリー・ゴライトリーだ。肩書は“女優”だけど、本当は何者かよく分からない女の子。映画ではオードリー・ヘプバーンがホリーを演じている。彼女が住んでいるのは、高級住宅地アッパー・イーストの小さなアパートメント。部屋はリビングと小さなキッチン、ベッドルームという間取りだ。部屋の中は意外なほど物が少ない。新たにアパートの住人になったポールが「君も越してきたばかりなんだね」とホリーに言うのも無理はないほどだ。自分の名刺に“旅行中”と書くホリー・ゴライトリーは細々した物をトランクにしまっている。電話もベルがうるさいからという理由で、トランクに入れたきりだ。彼女はドアの横に大・中・小の白いトランクを積み上げて置いている。基本的にはここに収納できる物だけを所有して、いざとなったらその三つのトランクを抱えて出ていくつもりなのだろう。ホリーの性格がよく出ている小物だ。
バスタブを切って作ったソファ
ガランとしたホリーの部屋で目につくのは、鮮やかな紫のシートとフクシア・ピンクのクッションが印象的な白いソファ。しかしよく見るとこれは猫足のバスタブを半分に切ってD.I.Y.で作った物だと分かる。ゼブラ柄の敷物の上に貨物用の木箱をコーヒー・テーブル代わりに置いて、彼女のリビング・セットは出来上がり。
金のまつげがついたアイマスク
ホリー・ゴライトリーはパーティ・ガールなので、しょっちゅう朝帰りしてくる。夜明けにタクシーで五番街まで戻ってきてティファニーのウィンドウ前でデニッシュとコーヒーの朝食を済ませ、それから午前中いっぱいアパートで寝ている感じだろうか。当然、窓から差し込んでくる光が眩しいのでアイマスク(と街の騒音をシャットダウンする耳栓)が就寝時に不可欠だ。ホリーがしているアイマスクは水色のサテンで、金のまつげが飾りでついた洒落た一品。後ろボタンの男物のタキシード・シャツを寝巻き/部屋着代わりに着ているのが可愛い。
オフタートルのプルオーバー
「ティファニーで朝食を」に限らず、オードリー・ヘプバーンの映画の衣装というとユベール・ド・ジバンシィのデザインしたシックなドレスが話題になる。ホリーの衣装も、有名な黒のドレス二種は彼の手による物だ。しかし、今見て参考になりそうなのは、ドレスアップしていないホリーの普段着の方。こちらは衣装デザイナーのイーディス・ヘッドが手がけている。ホリーが映画のラストに着ているのは、グレイのオフタートルのプルオーバー。何気ないアイテムだが、黒のスリムパンツと合わせてダウンタウンのビートニク風ファッションに仕上げている。これにトレンチ・コートを合わせれば、黒のドレスとコスチューム・ジュエリーというよくあるコスプレとは違う、リアル・クローズ版ホリー・ゴライトリー・スタイルになる。
ヴィンテージ・チェアのあるアパートメント
次は現代のニューヨークのヒロイン。リーマン・ショック後の映画では、若者たちを描く時も経済的な背景が不可欠。ノア・バームバック監督の「フランシス・ハ」(2014)で、脚本も共同で手がけたグレタ・ガーウィグが演じるヒロインのフランシスの職業はダンサー。いつもお財布の中身は覚束ない。
フランシスは最初、ブルックリンで大学時代からの親友、ソフィーとルーム・シェアをしているが、ソフィーがもっと家賃の高いマンハッタンのトライベッカ地区に引っ越すと言い出して、同居を解消せざるを得なくなる。引っ越す前のフランシスの部屋に置かれているのはヴェルナー・パントンがデザインしたSystem 1-2-3シリーズのダイニング・チェアによく似た物。オリジナルかレプリカかは分からないが、シンプルな部屋のアクセントになっている。
レヴの持っているポラロイド・カメラ
そこで彼女が一緒に暮らし始めたのが、レヴとベンジーという自称“アーティスト”の男子たち。彼らが暮らすチャイナタウンのシェアハウスはリビングに大きなレコード棚があり、いかにも今時の趣味のいいヒップスターのインテリアといった感じだ。遊びに来たソフィーが「あの椅子はイームズ?」と聞くシーンがあるが、チャールズ・イームズが1950年代にオフィス家具メーカーのハーマン・ミラーのためにデザインした椅子だけではなく、このシェアハウスのあちこちにヴィンテージ家具が置かれている。リビングにあるのはフィンランドのデザイナー、エール・アールニオが1963年に発表したボール・チェアだ。レヴを演じるのは今をときめくアダム・ドライバー。レヴはお気に入りの雑貨もレトロだ。フランシスが初めて彼の部屋に遊びに来た時には「これもヴィンテージなんだ」とポラロイド・カメラを自慢している。アダム・ドライバーはノア・バームバックの「ヤングアダルト・ニューヨーク」(2015)でもフェドラとフィルム・カメラ、アナログ・レコード、V H Sテープを愛するヒップスターを好演した。
「トリュフォーの思春期」のポスター
実は「フランシス・ハ」で使われているチャイナタウンの部屋は、グレタ・ガーウィグが出演当時、この映画のプロデューサーであるオスカー・バイソンとプロダクション・デザイナーのサム・リセンコとシェアしていたところ。この二人は「フランシス・ハ」以外にも「グッド・タイム」(2017)「アンカット・ダイヤモンド」(2019)などのサフディ兄弟の映画で活躍している。グレタとこの二人の実際のインテリア趣味がのぞくのが、リビングに貼られた映画「トリュフォーの思春期」(1976)のイラスト・ポスターだ。ウェス・アンダーソンもフェイバリットに挙げるこの映画を、グレタたちも好きだったのかもしれない。
フランシスの着る花柄プリントのワンピース
デヴィッド・ボウイの「モダン・ラブ」が流れる印象的なシーンで、フランシスが着ているのが古着っぽい花柄プリントのワンピース。彼女はそれにレザー・ジャンパーを羽織り、下に黒のパンツをはいている。靴はコンバースのハイカット。この場面に限らず、フランシスは古着のプリント・ワンピースにスパッツを合わせていることが多い。フランシスのように自由に走って、そして時々転ぶのに最適なスタイルだ。
ソーホーのロフトに置かれたミニチュアの家具
「ティファニーで朝食を」や「フランシス・ハ」のヒロインは地方からの上京組だが、自身が監督・脚本も手がける「タイニー・ファニチャー」(2010)でレナ・ダナムが演じるオーラは、マンハッタン出身の都会っ子。彼女は大学を卒業して、逆にニューヨークの実家に戻ってくる。オーラの母親シリは有名なアーティストで、トライベッカのロフトは半分、彼女のスタジオになっている。オーラが家に帰った時に彼女が作っているのが、ミニチュアの家具を使った写真作品。白い作り付けの棚がスタイリッシュなロフトに、カラフルなミニチュア家具は映える。このロフトは実際のレナ・ダナムの実家で、母親役を演じるのも彼女の本当の母親、アーティストのローリー・シモンズだ。
リビングにあるヴァーパンのV P G L O B E 50のペンダントランプ
監督本人の実家といっても、レナ・ダナムの家は両親共々有名なアーティストだけあって、隅々までスタイリッシュである。こんなところに住めるのならば文句はないはずだが、定職につかず、具体的な将来のビジョンもないオーラは居心地の悪い思いをしている。彼女が疎外感を味わうダイニングに吊るされているのが、デンマークのデザイナー、ヴェルナー・パントンの60年代の作品G L O B E 50。シェードをアクリルの球体で覆った有名なライトだ。ニューヨークの洗練された住居には、ミッドセンチュリーの家具がよく似合う。
ジェドが読むウディ・アレンの「羽根むしられて」
母親がいない隙にオーラが自宅に泊めるのが、コメディ作家のジェド(アレックス・カポヴスキー)。彼がベッドで読んでいるのがウディ・アレンの二冊目のユーモア短編集「羽根むしられて」。彼の有名な一幕劇「死」と「神」も収録されている。これだけで、ジェドがどんなユーモア・センスの持ち主かよく分かる。
オーラの着ている襟が三重になったブラウス
オーラのファッションは基本的にカジュアルだが、時折少女っぽい可愛らしい服を着ることもある。どこかひねりのあるデザインのものが多く、アーティスティックな環境で育った彼女のバックボーンを思わせる。両親がいない隙に、妹が勝手に人を招いてパーティを開いてしまった時にオーラが着ているのは、丸襟が三重になっているブラウス。それぞれの襟に違うステッチが入っているところがキュートだ。
60年代でも、2010年代でも、ヒロインたちは大都会で自由に生きることを渇望している。部屋に置かれた物や身につける物といった小さなディテールに彼女たちの個性が瞬き、それがマンハッタンの夜景とはまた違う小さな光となって、ニューヨークを輝くものにしているのかもしれない。