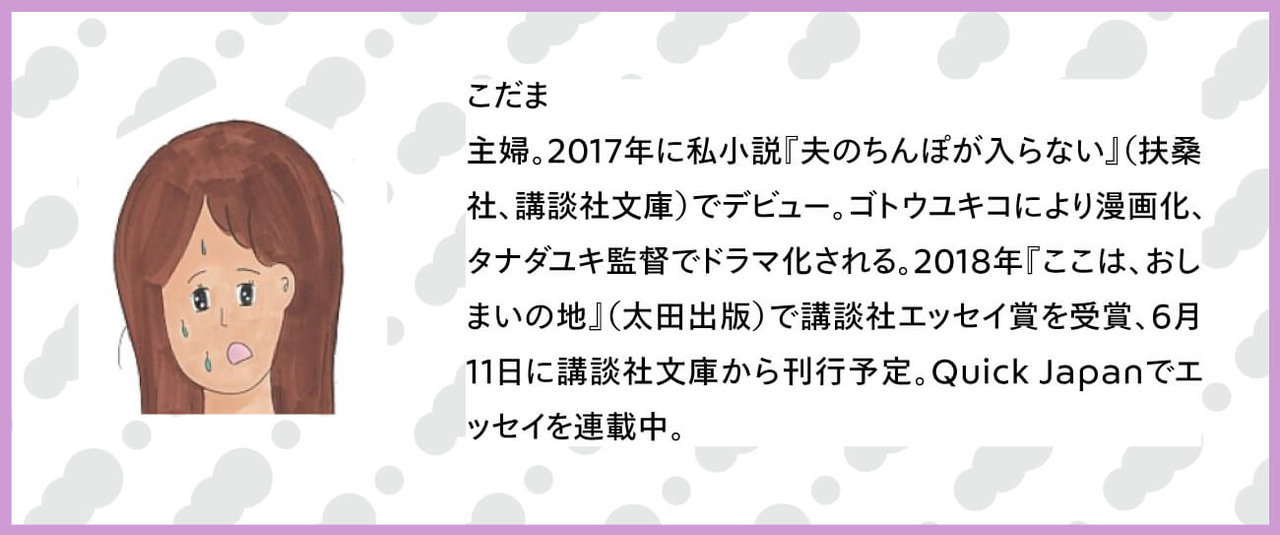みんなはいま、どんな時間を過ごしているのだろう。
こんなときだからこそ、普段は人に見せない「おうち時間」を、ちょっとのぞかせてもらえませんか――メルカリマガジンのそんなお願いに、さまざまな書き手の方が〈寄稿〉というかたちで参加してくださいます。
誰かの孤独で密やかな時間が、ほかの誰かを安らげ応援することが、きっとある。「みんなのおうち時間」では、多様な家での過ごし方と、とっておきのお気に入りアイテムをご紹介していきます。
(文・写真/こだま、編集/メルカリマガジン編集部)
できるだけ家の中で過ごしましょう。
まさかそんなお願いをされる日が来るなんて思わなかった。
私の半生は「職に就いては辞める」の繰り返しだった。思うようにいかない情けなさに落ち込み、ひたすら引きこもる。やがて、何もせず家にいることに罪悪感が膨らみ、急き立てられるようにハローワークへと向かう。でも、次の仕事も長続きしない。それが私の人生のサイクルだった。
家の中にいるのが好きなのに、変な自意識と中途半端な真面目さから、いつも後ろめたさが付きまとっていた。だから急に「Stay Home」なんて言われたとき「これで堂々と引きこもっていられるぞ」と得意げになった。外へ遊びに出たがる人を見て「長年に渡って培ったインドア人間の腕の見せどころだ」と思った。家の中でも十分楽しいよ、と。
だけど、しばらくして、それは浅はかな考えだったと気付く。
おいしいパンを食べ、取り寄せた新刊を読み、お笑い番組を観ながら「やっぱり家が一番だな」と思えたのは、それを陰で支えてくれる人々がいたからだ。
今は暮らしの中のひとつひとつに「関わってくれた誰か」を強く感じる。こんな大変なときに売ってくれてありがとう、届けてくれてありがとうという気持ちになる。
外出自粛になっても特に困らないな、だって家が好きだもん。そんなことを平気で言っていた少し前の自分が恥ずかしい。
そう意識するようになった今、私の中で「おうち時間」は、もっと特別なものになった。
数年前まで夜勤のある仕事に就いていた。
午前9時、眩しい光に目を細めながら「お疲れさま」と解散し、その足でまっすぐ向かうのは銭湯だった。何も考えずに浴槽の縁に重い頭をもたげる。この時間が一晩がんばった自分へのささやかなご褒美だった。ところが、そのあと着替えて自宅に帰るのに苦労した。ほかほかになった身体が、自然と深い眠りへと誘う。帰り道、うとうとしてまっすぐ歩けなくなるのだ。
銭湯へ行かなくとも、どうにかして家のお風呂で特別感を味わえないだろうか。
そんな矢先、広大なラベンダー畑のある北海道の富良野に出掛けた。宿の浴室に、薄紙に包まれたラベンダーの固形石鹸があった。液体のボディソープに慣れていたので、普段なら気に留めなかっただろう。包装紙には風に揺れる紫の花が描かれていた。旅先特有の開放感から手に取ってみた。ラベンダーのやさしい香りがする。タオルで泡立てて洗い流すと、肌のしっとり感が違った。ほのかな香りも続く。いいじゃないか。
その日を境に、私の中で固形石鹸ブームが到来した。旅に出ると、その土地ならではの石鹸がないか探すようになった。あまりパッケージに気を遣ってない「われわれ苦瓜農家が作りました」といった素朴な謳い文句の品を発見すると、採れたての野菜を手にしたような喜びがある。百貨店の化粧品や雑貨売り場などもパトロールし、収集熱を高めていった。
悩みもあった。1個の石鹸を使い切るのに2、3ヶ月かかるのだ。早く次の香りを楽しみたい。せっかちで欲深い私は石鹸をナイフで切り、その日の気分で少しずつ試すようになった。ジャスミン、蜂蜜、柚子、オレンジ、オリーブ、ユーカリ。それだけで自宅のお風呂が急に豊かなものに変わった。
ワイヤー状の石鹸専用カッターなるものまで購入。新たな品を手に入れてはカッターを握り締め、しめしめ楽しませてもらうよ、とほくそ笑みながら切断する日々を送っている。
家で楽しめる趣味は他にもある。2年前からペン字を習い始めた。道具代や月謝がそれほどかからない、作業中できるだけ会話がない、最低限の人付き合いで済む。ペン字教室はこの条件を満たしていた。
ペンとインクと紙、そして毎月のお手本だけ。ペンを持っている間は話しかけられることがない。私の教室には高齢者が多いので飲み会に誘われることもない。最高だ。
習い事の日だけでなく、原稿に行き詰まるとペンを持つようになった。文化的逃避と呼んでいる。自然と背筋が伸びる。書道教室に通っていた子供時代に戻ったような気持ちで昇級をめざす。作品展にも出す。
高齢の師範から「あなたはなかなか筋が良い」と褒められた。仲間たちは加齢による手の震えで文字がゆがむらしい。「若い人は覚えが早いわ」などと、ちやほやしてくれる。お年寄りしか買わないような仏壇向きの和菓子をおみやげにくれる。そんな距離感も心地よい。まだまだ未知の世界が身近にあった。大人になって始める習い事もいいものだ。今は静かに教室の再開を待ち望んでいる。
最後に、忘れてはならないのが猫。私が家にこもる最大の理由だ。
路上で泥水を浴びてグショグショになっていた子猫を連れ帰り、この春で18年になる。キジトラ模様のおばあさん猫。簡単に人に懐かない、気に入らないとすぐ噛む、寒いときと空腹のときだけ寄ってくる、マタタビの実でへろへろになる。実に猫らしい猫だ。
お世辞にも綺麗な容姿とは言えない。まず、顔がこわい。小太りで脚が短く、団子のように縮んだ尻尾。見た目も性格も、誰にも飼ってもらえないような要素が多い。だからこそ「私たちだけの猫」という愛おしい感情が湧くのかもしれない。
最近、南から渡ってきたハクセキレイが我が家の屋根の隙間に巣を作り始めた。日中、鳥の影がカーテン越しに何度も行き来する。よく響く高い声でさえずる。森の中を散歩しているような清々しい気持ちになる。
家にいながら、こんな気分を味わえるなんて。うっとりする私の横で、猫は野性の本能を剥き出しにしてシャーと唸る。1日20時間くらい寝ていた猫が、今では睡眠時間を削って窓辺の巡視に費やしている。無理をしないでほしい、おばあさんなのだから。
何もしなくていい。ひなたで丸くなっているだけでいいから、あと2年くらいそばにいてほしい。そんな祈りを込めて、今日も小さな頭を撫でる。
こだま
主婦。2017年に私小説『夫のちんぽが入らない』(扶桑社、講談社文庫)でデビュー。ゴトウユキコにより漫画化、タナダユキ監督でドラマ化される。2018年『ここは、おしまいの地』(太田出版)で講談社エッセイ賞を受賞、6月11日に講談社文庫から刊行予定。Quick Japanでエッセイを連載中。